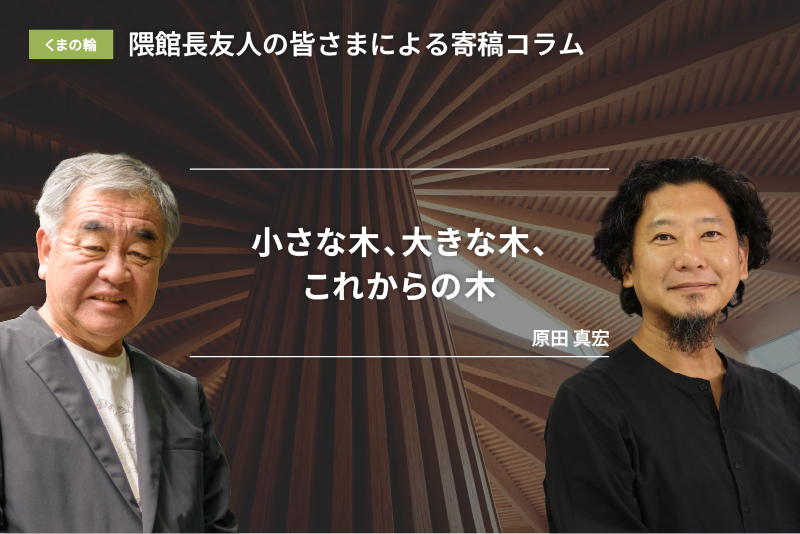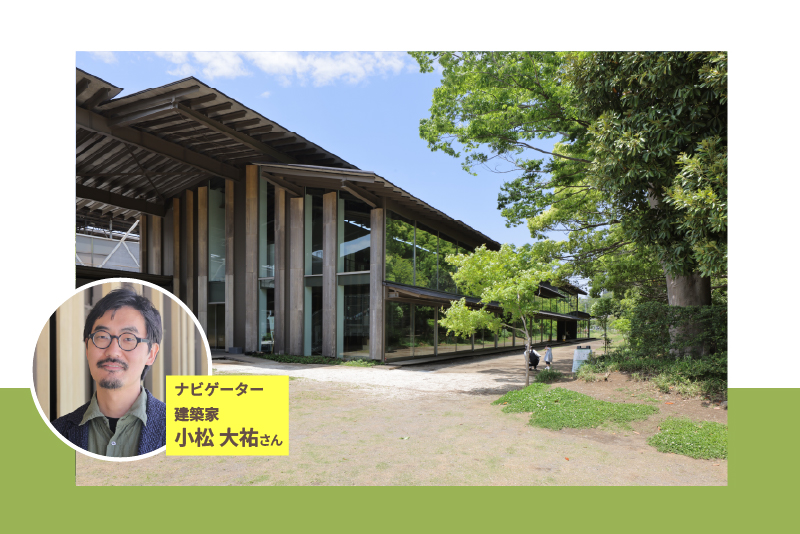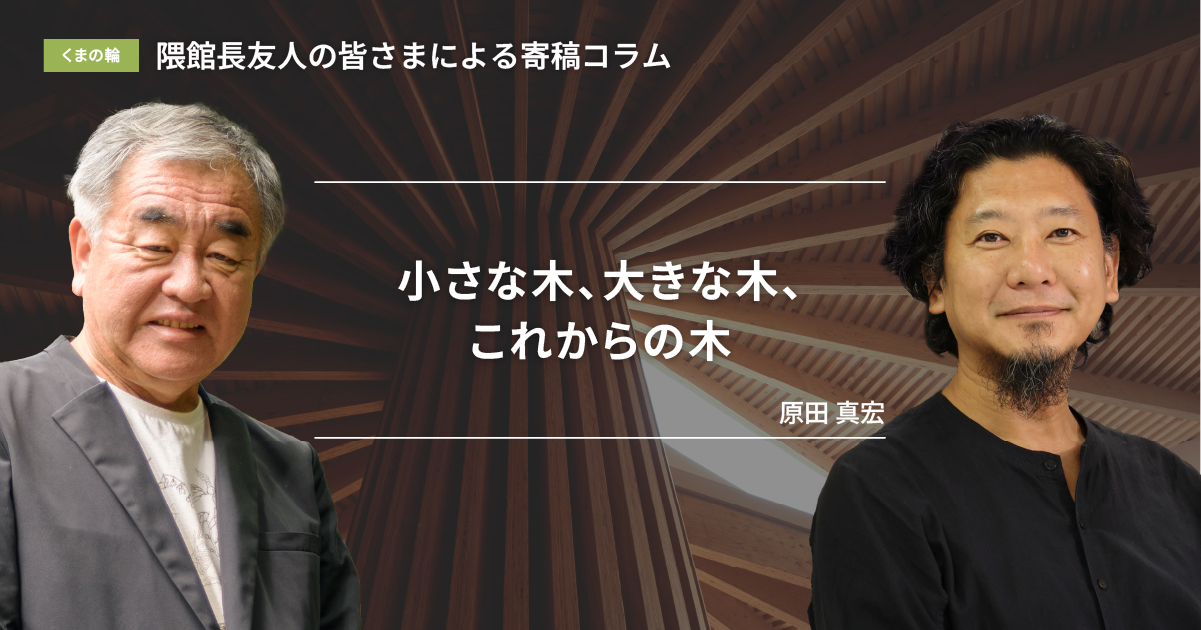

原田真宏(ハラダ マサヒロ)
MOUNT FUJI ARCHITECTS STUDIO 主宰建築家 / 芝浦工業大学 建築学部教授
1973年静岡県生まれ。97年芝浦工業大学大学院建設工学専攻修了(三井所清典研究室)、1997〜2000年隈研吾建築都市設計事務所、2001〜2002年文化庁芸術家海外派遣研修員制度を受けホセ・アントニオ & エリアス・トーレス アーキテクツ(バルセロナ)に所属、2003年磯崎新アトリエ。2004年に原田麻魚と共に「MOUNT FUJI ARCHITECTS STUDIO」を 設立。2005〜2006年慶應義塾大学 COE特別講師、2007年芝浦工業大学工学部建築学科非常勤講師、2007年慶應義塾大学理工学部システムデザイン工学科非常勤講師、2008〜2016
年芝浦工業大学工学部建築学科准教授、2014〜2015年東京大学工学部建築学科非常勤講師、2015年〜東北大学工学部建築・社会環境工学科非常勤講師、2016年芝浦工業大学工学部建築学科教授、2017年〜芝浦工業大学 建築学部建築学科教授。
主な建築作品
《道の駅ましこ》(2016)、《知立の寺子屋》(2016)、《Entô》(2021)、《STROOG》(2022)など。
受賞歴
JIA日本建築大賞(2017)、日本建築学会賞(2020)、BCS賞(2018)、(2021)、(2024)、(2025)など。
気が付けば、僕は多くの作品を「木」で実現してきたようだ。
なんだか人ごとのような言い方だけれど、数えてみると、僕のデザイン・キャリアの半分近くは「木造」が占めているのだから、それは僕の一つのキャラクターと言っても良いのだろう。
そんな訳で、処女作には作家の未来が全て詰まっているということでもあるし、デビュー時の話から始めることにしようかと思っている。
はじまりの木
僕のそれは「XXXX」(2003)と名付けられた、とてもとても小さな小屋である。
父親の趣味である陶芸のためのアトリエで、僕が生まれ育った実家の庭の片隅に、今も更新されながらもそのままの形で建っている。商売用に購入する予定だったトヨタカローラをやめて、その代わりにアトリエを建設するという算段だったから、予算は当時のカローラの価格150万円。今思えばなんとも無茶な話なんだけれど、バルセロナから帰国したばかりの僕には他に特にすることもなく、一も二もなく引き受けた、というわけだ。


しかし建築としてはあり得ないほどに少額な予算は、一般的な建築形式をもはや許しはしなかったから、根本から新しい形式を見出す必要があった。まず、こんな金額で引き受けてくれる工務店はない。だからセルフビルドが大前提。僕たち自身が施工するということは、素人でも扱える材料でなければならないし、運搬や施工に建設重機も使えない。それぞれ仕事もある人たちで作るのだから長期の施工期間も取れないだろう。さらには、予算は全くと言っていいほどにないのだからたくさんの材料は買えないし、当然高価な建材など使えはしない。
そんなエクストリームな背景条件の中、解決に導いてくれたのがホームセンターで出会った「普通構造用合板t12」である。いわゆるサブロク判コンパネ。今も覚えているけれど、そのとき1枚680円だった。これだけで作ることができれば、たった150万円でも父親が欲しがっているアトリエを実現できるかもしれない。。。
結局見出したのは、交互に左右に揺れる平行四辺形フレームを連結した、誰も見たこともない新しい建築形式である。X字型の連結部には三角形の開口部が上下に生まれ、作陶の手もとを照らすように自然光を取り込みつつ、それは強固なトラスとしても機能して、12mm厚の合板4枚を貼り重ねただけの華奢な部材でも構造を成立させてくれた(総厚48mmの木製パネルは構造だけでなく、断熱や仕上げ、サッシも兼ねる複合材料として機能している)。




言い換えれば、「強い形」を見つけることで、少なく弱い部材でも成立し、少ない材だから安く、少なさは軽さも意味し、軽いから重機も要らず手運びできて、弱い材は素人で簡単に手加工もでき、だから短い期間でも、、、といった具合に連鎖するようにして、背景条件全体に解決を与えてしまったのである。
こんな風に、僕にとっての「木造」は、木を使うこと自体が「目的」というわけではなくて、建築の背後に広がる環境条件への「解決」として始まっている。もっと踏み込んで表現すれば、環境条件が潜在的に要求している「新しく合理的な形式」を木の特性によって実現することが、僕のキャリアの原点に仕込まれていた、とも思うのだ。
最小の木
この合理的に木造建築を捉えるという方向性は、特に初期の頃の作品群では「構造的な合理性の探究」として展開していくことになった。一般的ないわゆる「在来木造」と呼ばれる建築では、例えば「壁量計算」等という、厳密な計算に基づいて、というよりも長年の経験則を頼りに構造を扱う方法が取られているが、その物理的な曖昧さを取り除きたいと考えていた。理性の光のもとでの新しい木造、を求めていた時期である。
具体的に作品を示すと、先ずは最初の住宅作品「おおきな家|m3/kg」(2006)ということになる。



寝室や収蔵庫等、セキュアな空間を内包する「L」字型のRCのパートに、LVL(Laminated Veneer Lumber|単板積層材)でできた「ロ」の字型の木造の開放的な空間を組み合わせた混構造の建築だ。エンジニアリングウッドの一種であるLVLは構造強度が工業製品のように数値で保証されているから、厳密な構造計算に乗せられる。木造部、RC部、そしてそれらの間で力を伝達する鉄骨部が、それぞれキチンと計算され過不足のない適切な全体として成立し、地震力をRC部に効率よく伝達できたことで、LVLの柱と梁は38mmほどのごく薄いフィン状のプロポーションで成立した。完成した空間は、その削ぎ落とされた部材寸法によってだろうか、背筋の通った明晰で硬質な空気をまとっていて、従来の木造建築の不確かな空間性(それも今は木造の一つの良さだとは思っているが)とは、明らかに一線を画したものだった。
このLVLを主構造に用いた、無駄のない木造の系譜は、放射線状にフレームが反復された「Tree House」(2009)、構造材厚30mmにまで最小化された「near house」(2010)、自然地形に沿って軸組がシフトした「Geo Metria」(2011)等を経て、天然木と組み合わせた「Shore House」(2013)へと至ったが、それらの試みの中で、Tree Houseの放射線状の幾何形態の性質上、空間の中心に生まれた「直径1.1mのLVL束ね柱」の巨大な印象が次の展開を生むことになった。