
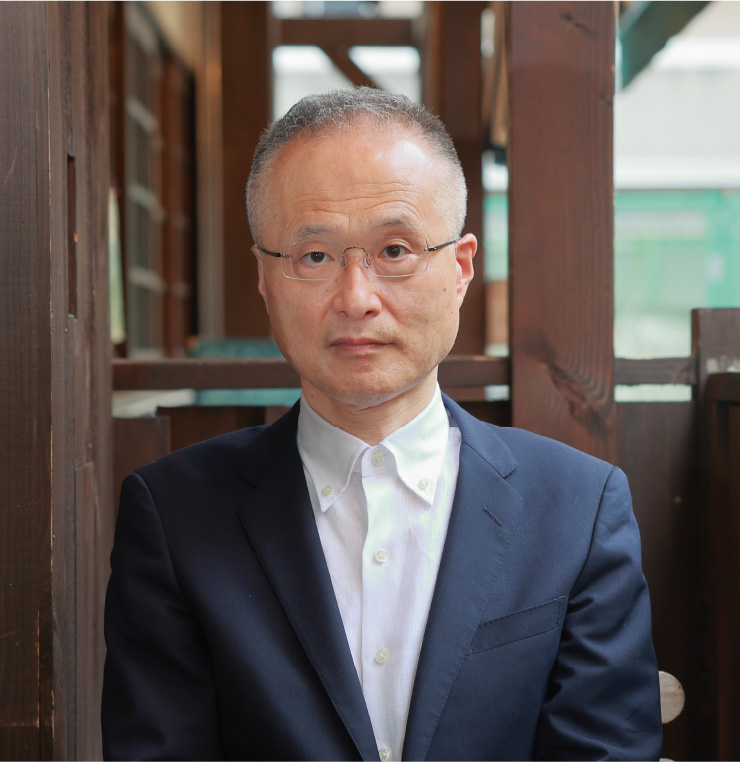
飯島 洋一(いいじま よういち)
1959年東京都生まれ。建築評論家、多摩美術大学教授。1983年早稲田大学理工学部建築学科卒、1985年同大学院建築計画専攻修士課程修了。1985年清水建設本社設計部(~88年)1995年多摩美術大学美術学部芸術学科助教授、1998年同環境デザイン学科助教授、2004年同環境デザイン学科教授、2008年同共通教育学科(現在、共通教育学科はリベラルアーツセンターに改称)教授。2003年にサントリー学芸賞受賞。著書に『「らしい」建築批判』『アンビルトの終わり』(以上、青土社)など。現在、毎日新聞の読書欄で、書評を定期的に執筆中。
著書
『光のドラマトゥルギー 20世紀の建築』青土社(1990)/『37人の建築家 現代建築の状況』福武ブックス(1990)/『建築のアポカリプス もう一つの20世紀精神史』青土社(1992)/『現代建築の50人』INAX出版・INAX叢書(1993)『アメリカ建築のアルケオロジー』青土社(1993)/『終末的建築症候群』PARCO出版、(1994)/『王の身体都市 昭和天皇の時代と建築』青土社(1996)/『映画のなかの現代建築』彰国社(1996)/『<ミシマ>から<オウム>へ 三島由紀夫と近代』平凡社選書(1998)/『現代建築・アウシュヴィッツ以後』青土社(2002)/『現代建築・テロ以前/以後』青土社(2002)/『キーワードで読む現代建築ガイド』平凡社新書(2003)/『建築と破壊 思想としての現代』青土社(2006)/『グラウンド・ゼロと現代建築』青土社(2006)/『破局論』青土社(2013)/『「らしい」建築批判』青土社(2014)/『建築と歴史 「戦災」から「震災」まで』青土社(2015)/『アンビルトの終わり ザハ・ハディドと新国立競技場』青土社(2020)
受賞歴
サントリー学芸賞(2003)
日本らしさを模索する戦後のモダニズム
戦後社会を迎えると、先のレーモンドが東京都心にアメリカの最新技術を徹底して駆使したコンクリートの『東京リーダーズダイジェストビル』(1951年)をつくり、大きな話題となった。その影響を受けたのが丹下健三の『広島ピースセンター』(1955年)である。さらに『広島ピースセンター』は桂離宮を一つの手本にしていたが、桂離宮の木造の伝統は、ここでもコンクリート造に置き換えられている。また1958年には丹下の『香川県庁舎』も完成したが、そこでは木造建築の梁や庇のデサインが、全て意図的に鉄筋コンクリートに置き換えられていた。このように戦後日本では、確かに日本の伝統は繰り返し話題になった。だが、それはコンクリートでつくる日本の伝統建築に限定された話である。吉田五十八のような近代数寄屋は別として、日本の伝統の事は戦後に幾度も思い出されたものの、木造建築の記憶は相変わらず「忘れられたまま」だった。


写真提供:大阪府立近つ飛鳥博物館
1970年代以降になると、丹下健三らのモダニストを批判する動きが出てくる。たとえば安藤忠雄が『住吉の長屋』(1976年)がそれである。ここでは江戸時代のかつての木造建築だった「長屋」を、木造でなく「コンクリート打ち放し」で置き換えている。『明治神宮宝物殿』と同じパターンである。こうして芸術美学としての「コンクリート打ち放し神話」が誕生する。そしてこの研ぎ澄まされたシンプルなコンクリート打ち放しは、「日本的なもの」を内包していると評価された。この「コンクリート打ち放し神話」は国内だけでなく、世界の建築界でも大きな力を持った。近代建築を最大限にまでブラッシュアップしたもの、それが「コンクリート打ち放し神話」だったからだ。だが、国内では1989年のバブル経済崩壊と同時に、この「コンクリート打ち放し神話」もまた同時に崩壊する。
自然や環境との調和を目指した、隈研吾の「負ける建築」
環境破壊はすでに1970年代から深刻化しており、近代社会の限界は指摘されていたが、バブル崩壊は、いわば明治以降の、とくに戦後日本以来の「近代社会の成長」そのものが、このままでは通用しないという事実を私たちに鋭く突きつけた。事実バブル崩壊の1990年代以後、日本は低成長のままである。
その中で、誰よりもいち早く、木などの自然素材を主軸にして、それまでの「コンクリート打ち放し神話」とは全く異なった、「脱近代の建築」に挑戦したのが隈研吾だった。しかも隈は、それを森林の豊富な地方の町で展開した。その地方での経験が役立って、隈が設計に携わった『国立競技場』(2019年)では、木と鉄のハイブリッドが採用され、単に「日本的である」だけでなく、そこには国産の木材がふんだんに使用されている。

林野長官賞・マロニエ建築賞・村野藤吾賞・BCS賞・日本建築学会選奨

明治以降の建築家たちのように、隈は日本の伝統を新素材で置き換えたりしない。彼は素材としても、日本の伝統の本来の在り方に着目する。こうして隈の建築によって、現代建築が日本の伝統の見直しをすると同時に、明治以来、「失われた木の記憶」が蘇えった。
隈が意図するのは、単に様式としての建築でも、実利としての建築でもない。それまで作家主義だった傾向を改めて、その建築を実際に使う人のこと、また環境や自然と調和する建築を考える。実際に隈自身の建築も国産の木材を使い、本当の意味で自然の中に溶け込んでいくものにする。隈にとって自然は闘うべき相手ではない。「人工物としての建築」をつくることで、「他者としての自然」を破壊してしまう部分が否めない。つまり建築は嫌でも勝ってしまう。だとしても、その建築の宿命を出来る限り制御しながら、自然と建築と人とが共生していくべきだ。これが隈の提唱する「負ける建築」である。
持続可能な社会に不可欠な、私たちの「木の記憶」
むろん、隈はいまさら文明開化以前の日本に戻ろうとしているのではない。そうではなく、明治以来、培った高度なテクノロジーは使用しながら、忘れられた「木の文化」を新しく復活させようとしているのである。脱炭素社会が叫ばれて、持続可能な社会を迎えるために、隈研吾がいま提唱する数々の自然素材の建築は、私たちがあまりにも便利な近代社会の中で、ずっと「忘却してきた木造建築」の記憶を日本文化の深層の中から「呼び戻す作業」である。そしてそれなしには、持続可能な社会は望めない。隈研吾の建築がいま大きく注目される理由も、ここにこそある。


隈館長による解説
飯島洋一さんは、ここでひとつの現代社会批判を行い、現代建築批判を行っているのだ。
飯島さんは、ここで一見対極とも見える二つの物を同時に批判している。
ひとつは、いわゆるコンクリートと鉄でできた近代建築であり、僕もはじめは木という自然素材を用いて、このような人工的素材を批判してきた。
しかし同時に、飯島さんは、いわゆる木造の数寄屋建築のようなものも同時に批判する。この二正面作戦は、きわめて新鮮である。



